機能性ディスペプシアの原因①
機能性ディスペプシア(機能性胃腸症・FD)の原因を東洋医学の観点で見てみましょう。
①脾胃虚弱(脾気虚)
脾は胃腸全体の消化吸収作用に関与する臓腑で、飲食物を消化吸収し気血に変化させ、その気血を運ぶ運化作用がある臓腑です。
脾の力が弱まると運化作用も弱まり飲食物の消化や気血の生成、運搬能力が低下します。
これが早期膨満感(消化吸収機能減退)、倦怠感や疲労感(気血不足)、吐き気や胃もたれ(飲食物を正常に運搬できない)の原因となります。
脾を動かす原動力は気で、これを脾気と言います。この脾気が減弱した状態を「脾気虚」と言い、機能性ディスペプシアの原因の大きな要因の一つです。
脾気虚は気を補う治療で改善します。
②胃食道性逆流症(胃気上逆)
機能性ディスペプシアは逆流性食道炎を併発する場合もあります。
食後のムカつきや吐き気、のどから胸のあたりにかけての痛みなどは胃酸の逆流によるものです。
これは胃の気が逆流する「胃気上逆」と言う状態です。
胃は口・食道から降りてきた飲食物を十二指腸、小腸へと下に送る力(降濁作用)を持っていますが、何らかの原因により胃気が逆流すると胃の内容物もそれに伴い逆流します。
空腹時なら胃酸やゲップ、食後なら吐き気として症状があらわれます。
胃気上逆を治すには脾胃の気の動きを整える治療をおこないます。
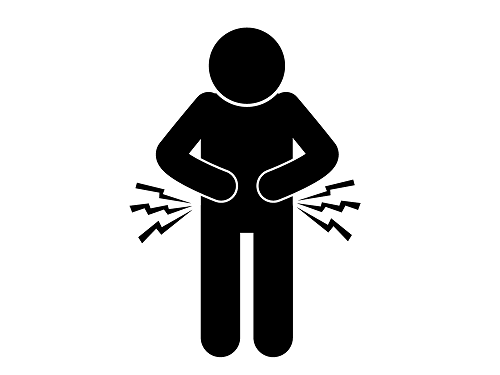
③ストレス(肝気犯胃・肝気犯脾)
肝は全身の気血の運行を調整する疏泄作用と言うものを持っている臓腑で、強いストレスや、継続してストレスを受け続けると肝の疏泄作用が乱れます。
脾の運化作用や胃の降濁作用も肝の疏泄作用の補助を受けて動いています。
ストレスにより疏泄が乱れると、脾の運化や胃の降濁も乱れ、気血や飲食物の正常な運行・運搬ができなくなります。
ストレスが肝に悪影響を与えさらに胃腸に連鎖したもので、「肝気犯胃・肝気犯胃」と言い、肝と脾胃の治療を同時に行います。