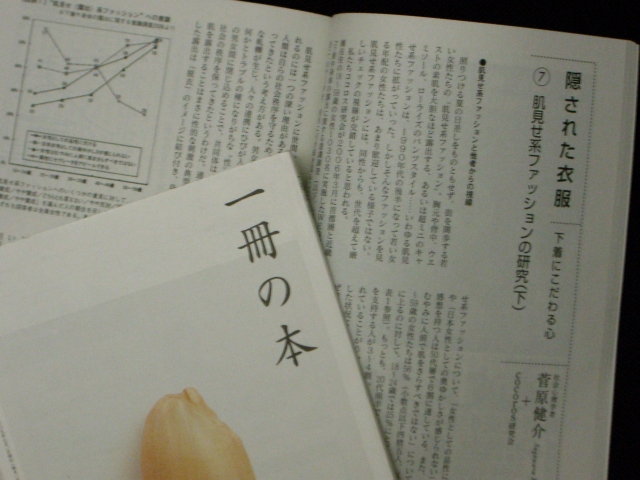
20100208
下着とココロの
真面目な
サイエンス
カイシャのシゴトだけれど、かれこれ4年間、大学の先生と共同で、「お気に入りの下着が、着用する人の心にどのような心理的効果をもたらすのか」をテーマにした研究を続けている。その経過を朝日新聞出版の月間誌『一冊の本』に、昨年7月号から連載してきた。私がゴーストライターとなって原稿案を作成し、それを先生が修正加筆し、また私が微修正させていただくといった共同作業だ。
研究対象は婦人洋装下着が中心となる。直裁的にはブラジャーやショーツ。女性の方々が、自分の気に入ったブラやショーツなどを選んで着けることで、その日の気分をどのように変えているのか、アンケートやグループインタビューで実態を明らかにしていく。女性のほぼ9割が、日々、デザインやつけ心地で「お気に入り」の下着を選んで着用し、自分の魅力をアピールしたり、気合を入れたり、心を安らげたりする心理的効果を得ていることがわかった。男性の場合も比較調査したが、年齢や所得差に関わらず、3割が女性の場合と近い「パンツこだわり派」であり、心の癒しの効果では、パンツから、女性の場合に匹敵する影響を受けていることが示された。下着は、つける人の生き方に、影響を与えているのだ。かすかな影響であろうが、下着はほとんど1日じゅう、皮膚に触れ続けている。四六時中スキンシップしている、最もカラダとココロに近い物体なのだ。
男女のべ七千人に調査してきたが、ようやく先生と連名の論文が、学会誌に掲載されることが決まった。にしても、たかが下着に、そこまで真面目な学術調査がなぜ必要なのか、呆れる方もおられるかと思う。
研究を始めた最初の疑問は単純だった。「なぜ、他人に見せるつもりのない下着に、人(特に女性)はこだわるのだろう?」。男性の下着に比べて、女性の下着には、多様なカラーに加えて、レースやリボンといった装飾が施されているものが多い。何故だろうか。今夜は親しい異性に、自分の下着姿を見せるかも……といった、いわゆる勝負下着のように「他者に見せる」ケースが、毎日連続しているわけではないだろう。それに、調査によると、下着にこだわるのは若い女性ばかりではない。年齢が60代でも、2割ほどが「恋人に下着姿をほめられると嬉しい」と答え、下着のファッションに強いこだわりを持っている。他者に見せないのなら、見た目のデザインなど気にしなくてもよさそうなのに、それでも、こだわる。何故なのか。動物にはない、人間だけが進化でかちえた特質なのだろうか。
もうひとつの大きな謎は、ブラジャーやコルセットといった婦人洋装下着が日本の女性にあまねく普及したのは、終戦後であるということだ。戦前は、大半の女性にとって、普段着はキモノだったから、日常的に洋装下着を着用する文化は、ここ60年ばかりの歴史しか持たない。ということは、最初は日本女性にとって影も形もなかった洋装下着が、ここ半世紀ばかりの間に、衣服の下に隠されながら、女性の心理にさまざまな影響を与えるアイテムとして、いわば「不可視の文化」を築き上げてきたことになる。何故、このような現象が起こったのか。これは現代の女性が複雑で厳しい社会を生きていくために、下着すら「心理的資源」に変えて、自分を元気づけるために活用するという、たくましい生活の知恵なのだろうか?
……といった、一見あたりまえのようで、実はけっこう謎に満ちた下着ワールドに、初めて心理学という学問のメスが入ろうとしている。たかが下着ではある。とはいえ、「他者に見せないのに、こだわる」とは、「自分だけのために、こだわる」ことだ。言いかえれば「自分のために、生きる」ことであろうか。だとすれば、下着へのこだわり方に、人が自分の存在をどのようにとらえようとし、あるいは、自分の存在を確かめようとしているのか、そういった「自己への愛」といったものを、かいま見せているのかもしれない。そこに、人が生きていく上で根源的な要素となる何かが発見できるのではないか。
「他者に見せることも、知らせることもない不可視の物ですら心の資源に変換し、自分が生きていく力に加えることができる」という「自らを愛し、より良く生きるミッション」が、ヒトの心の中にプログラミングされているとしたら……。
「ヒトは一人では生きられない」というNHK的常套句に、誰も疑いを差し挟まなくなって、どれくらいになるのだろうか。仲間外れにされた孤独な人間を絶望の淵へ追いやるこの言葉は、ここ四半世紀で異常に増殖してきた未婚単身生活者にとって、通用しなくなっている。
理屈抜き、好むと好まざるとに関わらず、30代前半の男性は半数以上が未婚者なのだ。50代の生涯未婚率も、すでに二割に達していることだろう。「無縁社会」などと気取っているどころではない。うかうかしていると、単身生活者が人口の過半数を占めてしまう。今や理屈抜きで、「ヒトは一人でも生きなくてはならない」のだ。人工の密集する巨大都市でも、そしてわずかな老人を時折り見かけるだけの過疎地の寒村でも、現代の日本人の多くは一人ぼっちのロビンソン・クルーソーでしかない。失業し、ネットカフェで寝泊りするしかなくなったら、終身刑を宣告されて独房に幽閉されたエドモン・ダンテスと変わらないではないか。そんな現実社会において、心の平静を保って前向きに生きていこうとするならば、ヒトは、自分一人だけで、自分の存在を肯定し続けなくてはならない。否応なく、「自分自身の愛し方」を磨かざるを得ないだろう。
他者に見せることなく一人フィギュアを愛でる人も、他社が見て痛々しいコスプレに耽溺できる人も、そうした生き方のバリエーションかもしれない。
はからずも、「お気に入り下着へのこだわり」にそのような社会背景が、おぼろげに重なってくるような気もする。もちろん断定することはできないが。
より良く生きようとするがゆえに、人類はパンツにすら愛を込めるのだ……という珍説がSFのネタになるかどうかは別として、これもソーシャル・サイエンスのひとつだろう。
それにしても、「人は一人では生きていけない」という言葉が社会に蔓延したのは、いつごろからだろう。60年ほど昔、終戦直後の日本では戦災孤児が下町にあふれ、餓死する子供もあたりまえのように身近である状況で、「一人でもしっかり生きていくのよ」と叱咤される時代だったように思う。人の生はどうあれ、死を見つめると、誰だって独りぼっちだ。誰かをあの世まで道連れにできるという保証はない。
だから、一人で生きることは、決して、社会からつまはじきにされた負け犬の生き方ではないと思う。昔から、いかなる組織にも他人にも頼らず、寂しさに泣き言をこぼすこともなく、一人で堂々と生きていくアウトローはかっこよく、英雄視されてきたではないか。その偶像の代表は、映画『カサブランカ』でハンフリー・ボガートが演じるダンディーなオトコであり、また『市民ケーン』を地のままに快演したオーソン・ウェルズであろう。一人で生きること、自分なりに工夫して、自分だけの幸せを持って生きていくことは、これからの時代、決して恥ずかしいことではないはずである。
結論は……なんのことはない、昔から、「一人で立派に生きていける」人こそ魅力的であり、周囲から信頼され、人望を厚め、その結果、孤独になりたくてもなれないほどの人気者になってしまうということだ。
一人で生きることは、決して人生の敗残者ではない。多数の仲間とともに生きることが、集団への依存ということでもあるまい。要はそこで、「誇りを持って生きる」ことができるか否か、ただ、それだけのことなのだ。
朝日新聞出版『一冊の本』での連載には、予想外の労力を要した。そもそも女性下着など、心理学の世界ではほとんど全く、研究されてこなかったのだ。真面目に研究したくても、女性の皆さんから、怪しい趣味でやっていると思われかねないし。それに、怪しいに加えて妖艶な下着の本は、昔から山ほど出ているし……ということで、Hなマッド・サイエ
ンス扱いされかねない。まずは、性的な好奇心とは一線を画した研究であることをきちんと説明せねばならず、私によってこの研究に引っぱり込まれた先生の当惑と御心労には、ただ深謝するばかりだ。『一冊の本』の連載は今年3月号でいったん終了し、その後は加筆して、単行本の出版を検討していくことになる。実現すれば、本邦初、もしかすると世界初の、下着心理学の学術書になるだろう。たかが下着といえども、そこは前人未到の新開地だ。考えようによっては、下着ワールドは、カーク船長も踏みこまなかった人類最後のファイナル・フロンティアとなりうるのかも……しれない。
それはそれとして、早く自分のSFを書きたい。本当に書きたい。充電期間にはなっているが、時間と気力のバランスがなかなかとれなくて。下着ホラーや下着SFはもちろんのこと、それとは別の作品の構想はあるし、少しずつ前進しているのだが……。
|

